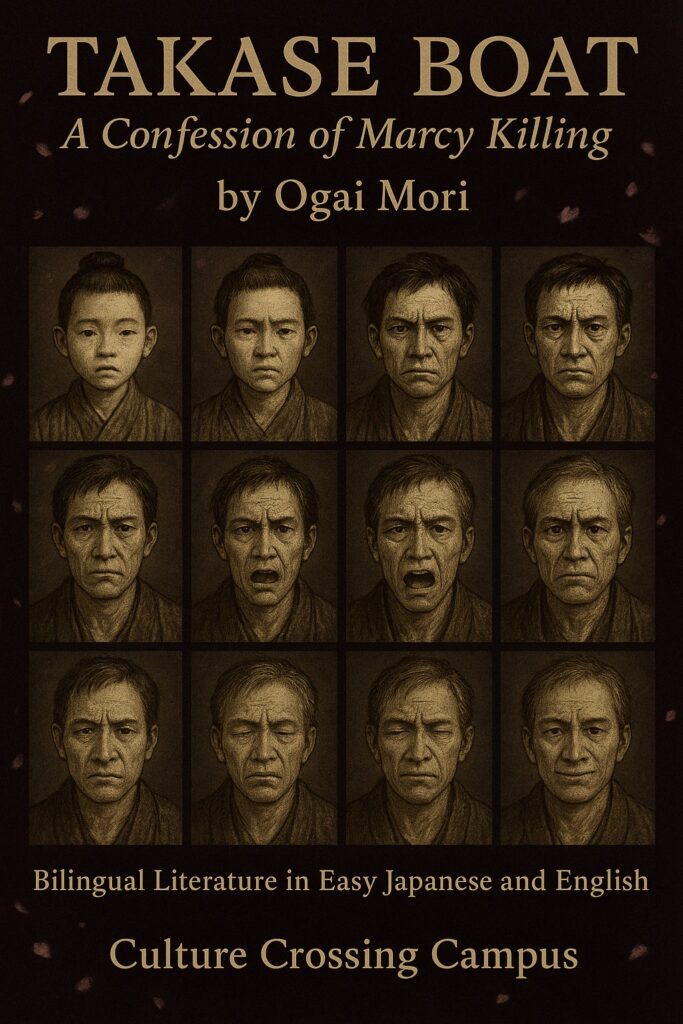
The Takase boat was a small boat that went up and down the Takase River in Kyoto. In the Edo period, when a person in Kyoto was punished with banishment to an island (Entō), his family was called to the jail to say goodbye. After that, the prisoner was put on the Takase boat and sent to Osaka. The prisoner was guarded by a dōshin (a low-ranking police officer working for the Kyoto magistrate’s office). It was a custom that one close family member of the prisoner was allowed to ride on the same boat to Osaka. This was not an official law, but the office allowed it quietly.
At that time, people who were sent to the islands were of course judged as serious criminals. But most of them were not very cruel people, like murderers or people who start fires on purpose. Many of them had only made a big mistake by accident. For example, some men tried “double suicide” (aitai-shi) with a woman. But sometimes, the man killed the woman and survived alone.
The Takase boat left Kyoto in the evening, when the temple bell rang. The boat moved east, passing the black houses of the town on both sides, and then crossed the Kamo River to go down. Inside the boat, the prisoner and his family talked about their life stories all night. They always repeated sad words of regret, things that could never be changed. The dōshin, sitting beside them, could hear these stories and learn about the difficult lives of the prisoner’s family. These were things that the town officers could never know by just reading official papers or hearing formal statements.
There were different kinds of dōshin. Some thought it was only noisy talk and did not want to listen. But others felt deep sympathy and pain in their hearts, even if they did not show it. When a very soft-hearted dōshin escorted a sad prisoner and family, he sometimes could not stop his tears.
Because of this, many dōshin disliked the duty of guarding prisoners on the Takase boat.
Chapter 2
It was probably in the Kansei era (around 1790s), when Matsudaira Sadanobu, a famous leader, was in power. On a spring evening, when the cherry blossoms of Chion-in Temple were falling with the sound of the evening bell, a very unusual prisoner was put on the Takase boat. His name was Kisuke, about thirty years old, a man without a fixed home. He had no relatives, so nobody came to the jail, and he had to ride the boat alone.
The dōshin who was told to guard him and go with him on the boat was Haneda Shobei. He only knew that Kisuke was a prisoner who had killed his younger brother. On the way from the jail to the pier, Shobei saw Kisuke’s pale and thin face. Kisuke looked very calm and very polite. He respected Haneda as an official and never tried to resist. But it was not like other prisoners, who sometimes only pretended to be gentle to please the guards.
Shobei thought it was strange. After they got on the boat, he did not only watch him as a duty, but also paid close attention to Kisuke’s behavior.
That evening, the wind stopped. Thin clouds covered the sky and made the moon look weak. The warm air of summer was coming, and it seemed like mist was rising from the soil of the river. When the boat left Shimogyō town and crossed the Kamo River, everything became quiet. Only the soft sound of water at the bow of the boat could be heard.
Prisoners were usually allowed to lie down and sleep in the night boat. But Kisuke did not lie down. He only looked up at the moonlight, which became stronger or weaker through the clouds, and stayed silent. His face looked bright, and there was a small light in his eyes.
Shobei did not look straight at him, but he never took his eyes away from Kisuke. In his heart he repeated, “Strange, strange.” Kisuke’s face looked happy from any side. If he had not been under the eyes of an officer, it seemed he might start to whistle or sing.
Shobei thought: “I have guarded many prisoners on this Takase boat. They all looked very sad and pitiful. But this man is different. He looks like he is on a pleasure boat. They say he killed his brother. Maybe his brother was a bad man, and maybe there was some reason to kill him. But still, no normal person should feel happy after that. Could this pale, thin man be a very rare kind of evil person, with no human feelings? No, it does not look like that. Maybe he has lost his mind? But if he were crazy, his words or actions would be strange. Yet everything he does is natural. What is this man…?” The more Shobei thought about Kisuke, the less he understood him.
Chapter 3
After a while, Shobei could not stop himself and spoke. “Kisuke. What are you thinking about?”
“Yes,” Kisuke answered, looking around. He sat up straight, as if he thought the officer had found some mistake. He carefully watched Shobei’s face.
Shobei felt he must explain why he asked such a sudden question. He also wanted to speak not only as an officer, but as a man. So he said: “No, there is no special reason. I just wanted to ask what you feel about going to the island. I have taken many people on this boat to the island. They were from many different lives, but all of them were sad. They cried all night together with their family. But when I look at you, you do not seem to be sad. What do you really feel?”
Kisuke smiled. “Thank you for asking kindly. Yes, going to the island is very sad for most people. I can understand that feeling. But that is because they had an easy life before. Kyoto is a wonderful place, but the suffering I had here was worse than any other place. The government (okami) showed mercy and saved my life, and now they send me to an island. The island may be hard, but it is not a place of demons. Until now, I never had a real place to belong. Now the government tells me to live on the island. I can finally stay in one place. That is the most thankful thing for me. Also, I look weak, but I have never been sick. So even if I must do hard work on the island, I think I will not hurt my body. And when I was sent away, I received 200 mon (coins). I have it here with me.” He put his hand on his chest. At that time, it was the rule that a criminal sent to an island received 200 mon.
Kisuke continued: “I must say something shameful. Until today, I never had 200 mon of my own. I always looked for work, and when I found it, I worked hard. But the money I earned always went out quickly. If I could buy food with cash, that was already a lucky day. Usually I had to pay debts and borrow again. But after I entered the prison, I could eat without working. I already felt sorry to the government for that. Then, when I left the prison, I received this 200 mon. Now, even while eating the government’s food, I can keep this money. This is the first time in my life I can hold money as my own. I don’t know what kind of work I can do on the island, but I am happy to think I can use this 200 mon as my first capital for work.” After saying this, Kisuke became silent.
Shobei said only, “I see.” But every word was so unexpected that he could not say more. He just thought quietly.
Chapter4
Shobei was at the age when a person begins to grow old. He already had a wife and four children, and his old mother was still alive. So, seven people lived in his house. He lived very simply and saved money so much that people sometimes called him “cheap.” He made only two kinds of clothes for himself: the clothes for his work and his sleeping clothes. But his wife came from a rich merchant family. She wanted to live only on her husband’s pay, but she had grown up in a rich home and could not save as strictly as her husband wished. Often at the end of the month, the money was not enough. Then his wife secretly brought money from her parents’ house to cover the shortage. She did this because her husband hated borrowing money. Of course, such things could not stay secret forever. Shobei felt ashamed even when his wife’s family gave gifts, such as clothes for their children or food for holidays. So when he noticed that his wife used money from her family to help their life, he did not feel happy. Their home was usually peaceful, but sometimes quarrels happened because of this problem.
Now, after hearing Kisuke’s story, Shobei compared it with his own life. Kisuke said he always had to spend his pay at once, without saving anything. That was a sad life. But when Shobei thought carefully, his own life was not so different. He also received pay and spent it all without saving. The only difference between them was the size of money. And unlike Kisuke, he did not even have savings like Kisuke’s two hundred mon coins.
So, it was natural that Kisuke felt happy about his small savings. Shobei could understand that. But still, he wondered why Kisuke had no greed and was satisfied with so little.
Kisuke had always struggled to find work. But when he found work, he worked hard and was satisfied with only enough money to buy food. So when he went into prison, he was surprised that he could get food without working. He felt a kind of happiness he had never known before.
Shobei now saw the big difference between himself and Kisuke. His own life was not rich, but it was usually balanced. Still, he never felt real satisfaction. He usually lived without thinking if he was happy or unhappy, but deep in his heart he always had fears: “What if I lose my job? What if I get a serious illness?” And when he learned that his wife used money from her family to cover their needs, these fears grew stronger.
Where did this difference come from? At first, it seemed simple: Kisuke had no family to support, but Shobei did. But Shobei thought that was not the real reason. Even if he were alone, he could not live with a heart like Kisuke’s. The truth must lie deeper.
He began to think about human life. When a person is sick, he wishes to be healthy. When a person has no food, he wishes for food. When there are no savings, he wishes for a little. And when he has some savings, he wishes for more. People’s wishes go on and on, and it is hard to know where to stop. Kisuke, however, was showing him the power of “stopping.”
Shobei looked at Kisuke with new eyes. He suddenly felt as if a light was shining from Kisuke’s head as he looked up at the sky.
Chapter 5
Shobei looked at Kisuke’s face and called him again, this time saying “Kisuke-san(like saying ‘Mr.Kisuke in Japanese’).” He did not really mean to change the way he called him. As soon as he heard the word from his own mouth, he realized it was not the right way to speak. But he could not take it back.
Kisuke answered, “Yes,” but he looked a little surprised. He seemed to wonder why Shobei called him “-san,” and he carefully watched Shobei’s face.
Shobei felt a little uneasy, but he said, “I hear many things about you. They say you are sent to the island because you killed someone. Please tell me the truth about it.”
Kisuke looked very humble and said quietly, “Yes, I will tell you. I did a terrible thing by mistake. Even now, I cannot understand how I could do such a thing. It feels like a dream. When I was a child, both my parents died of sickness, and only my younger brother and I were left. At first, people in the neighborhood felt sorry for us, like for a poor puppy under the roof, and they gave us food. We did small jobs for them, and thanks to that, we did not starve or freeze. When we grew older, we always tried to stay together. We helped each other and worked together. Last autumn, both of us started working in a weaving place in Nishijin. I did a job called sorabiki (pulling the threads). But soon, my brother became sick and could not work anymore. At that time, we lived in a poor hut in Kitayama. Every day we crossed the bridge over the Kamiya River to go to the weaving place. In the evening, after work, I bought food and went home. My brother was always waiting for me, saying, ‘I am sorry, I am sorry, you have to work alone for both of us.’
One day, I came home as usual, but I found my brother lying face down on the futon. The place around him was full of blood. I was very shocked. I dropped the food in my hand and ran to him, crying, ‘What happened? What happened?’ My brother lifted his pale face, covered with blood from his cheeks to his chin, and looked at me. But he could not speak. Every time he breathed, the wound made a strange sound.
I could not understand what had happened. I asked, “What is wrong? Are you hurt?” and moved closer. My younger brother pushed himself up a little with his right hand, while his left hand held tightly under his chin. A lump of dark blood was coming through his fingers. He stopped me with his eyes and finally spoke with great effort. “I am sorry. Please forgive me. I have an illness that will not get better. I only wanted to leave this world early so that you would not suffer for me. I thought if I cut my throat, I would die quickly. But only air came out, and I could not die. I tried to push the razor in deeper and deeper, but it slipped to the side. The blade did not break. I think if you pull it out well, I can die. It is very hard for me to speak. Please help me and take it out. I beg you.” When he loosened his hand, his breathing became harder. I could not say anything; I only looked at the injury on his neck. It seems that my brother held a razor in his right hand and cut his throat sideways. That did not work, so he pushed the razor in very deeply. The handle was only about two inches out of the wound. I saw this and did not know what to do. I just looked at my brother’s face. He was staring at me. At last I said, “Wait. I will bring a doctor.” But my brother looked at me with pain and shook his head. “A doctor will not help. I am suffering. Please, do it quickly.” I felt completely lost. I could only keep looking at him. At such a time, words were not needed; his eyes spoke to me. They said, “Hurry, hurry.” His eyes grew sharper and sharper, until at last they looked at me with anger, as if I were his enemy. Seeing this, I felt I had no choice but to do as he asked. I said, “All right, I will help you take it out.” At that moment, his eyes changed completely, becoming clear and peaceful, full of relief and even happiness. I thought I had to do it all at once, so I hit my knee and leaned forward. My brother let go of his right hand, and he put the elbow of the hand that had been holding his throat on the floor. Then he lay down. I held the handle of the razor tightly and pulled it out. At that moment, the old woman from the neighborhood, who I had asked to help my brother while I was busy, opened the front door and came in. It was already getting quite dark inside, so I could not see clearly how much she had noticed. She only said “Ah!” and ran out, leaving the front door open. When I pulled out the razor, I only tried to do it quickly and straight. But it felt like I cut a part that had not been cut before. The blade was pointing outward, so it cut more on the outside. The old woman came in and then ran out again. I held the razor and watched her without thinking. Then I looked at my brother. He was not breathing anymore. A lot of blood was coming from his wound. After that, the town officials came and took me to the town office. Until then, I had left the razor beside me and looked at my brother’s face with half-open eyes.”
Kisuke looked a little down and spoke, looking up at Shobei from below. Then he dropped his eyes to his lap.
Kisuke’s story was very clear and logical. It was so clear that it might even seem too perfect. This was because, for about half a year, he had often remembered the events, and every time he was questioned at the town office or investigated at the magistrate’s office, he had carefully gone over the story again and again.
Shobei listened as if he could see the scene with his own eyes. But he could not stop wondering: was this really a case of a brother killing another brother? Was it really murder? Even after hearing everything, he could not answer this question. His brother had asked him to pull out the razor so he could die. Some people might say that Kisuke killed his brother. But it seems that his brother would have died soon anyway. He wanted to die quickly because he could not bear his suffering. Kisuke could not bear to see his brother in so much pain. He ended his brother’s suffering. Was this a crime? Killing someone is a crime, of course. But if it was done to end suffering, it made Shobei doubt what was right. He could not solve this doubt.
In Shobei’s mind, after thinking a lot, he felt he had to leave the judgment to someone higher than himself. He had to follow the magistrate’s decision. Shobei decided to accept the magistrate’s judgment as his own. Still, some questions remained in his heart, and he wanted to ask the magistrate directly.
In the quiet night that slowly grew darker, the Takase boat, carrying the two silent men, slid over the black surface of the water.
高瀬舟(たかせぶね)は、京都(きょうと)の高瀬川(たかせがわ)を行(い)ったり来(き)たりする小(ちい)さい舟(ふね)でした。徳川(とくがわ)時代(じだい)※江戸(えど)時代(じだい)1600-1868年(ねん)/京都(きょうと)で法律(ほうりつ)を破(やぶ)った人(ひと)が「遠島(えんとう)※遠(とお)い島(しま)へ送(おく)られる刑(けい)/」になったとき、その人(ひと)の親(しん)せきは牢屋敷(ろうやしき)※刑務所(けいむしょ)/に呼(よ)ばれました。そこで別(わか)れのあいさつをすることができました。そのあと罪人(ざいにん)※法律(ほうりつ)を破(やぶ)った人(ひと)/は高瀬舟(たかせぶね)に乗(の)せられて、大阪(おおさか)へ送(おく)られました。
罪人(ざいにん)を見張(みは)るのは、京都町奉行(きょうとまちぶぎょう)※京都(きょうと)の役所(やくしょ)/の役人(やくにん)でした。そして、この役人(やくにん)は、罪人(ざいにん)の親(しん)せきの中(なか)から一人(ひとり)だけ大阪(おおさか)まで舟(ふね)に乗(の)せることができました。これは正式(せいしき)に決(き)まったことではありませんでしたが、役所(やくしょ)が大目(おおめ)に見(み)ていたのです。
そのころ「遠島(えんとう)」の罪人(ざいにん)は、もちろんとても悪(わる)いことをしたと考(かんが)えられました。しかし、人(ひと)を殺(ころ)したり、火(ひ)をつけたりするような、ひどく悪(わる)い人(ひと)ばかりではありませんでした。ちょっとしたまちがいや思(おも)いちがいから法律(ほうりつ)を破(やぶ)ってしまった人(ひと)も多(おお)かったのです。たとえば「相対死(あいたいし)※恋人(こいびと)と一緒(いっしょ)に死(し)ぬこと/」をしようとして、相手(あいて)の女(おんな)の人(ひと)を殺(ころ)して、自分(じぶん)だけ生(い)き残(のこ)った男(おとこ)などです。
そういう罪人(ざいにん)を乗(の)せた高瀬舟(たかせぶね)は、夕方(ゆうがた)の鐘(かね)が鳴(な)るころに出発(しゅっぱつ)しました。舟(ふね)は黒(くろ)っぽい京都(きょうと)の町(まち)の家(いえ)を両岸(りょうがん)に見(み)ながら東(ひがし)へ進(すす)みました。そして、加茂川(かもがわ)を横切(よこぎ)って下(くだ)っていきました。舟(ふね)の中(なか)で罪人(ざいにん)とその親(しん)せきは、一晩中(ひとばんじゅう)、自分(じぶん)の人生(じんせい)を話(はな)し合(あ)いました。いつも「残念(ざんねん)でも戻(もど)すことのできない話(はなし)」ばかりでした。見張(みは)り役(やく)の役人(やくにん)はそれを横(よこ)で聞(き)き、罪人(ざいにん)の家族(かぞく)がとても苦(くる)しい生活(せいかつ)をしていことを知(し)ることができました。役所(やくしょ)で聞(き)く表面(ひょうめん)的(てき)な話(はなし)や書類(しょるい)からは、決(けっ)して知(し)ることのできない話(はなし)でした。
役人(やくにん)の中(なか)にもいろいろな人(ひと)がいました。ただうるさいと思(おも)って耳(みみ)をふさぎたい人(ひと)もいました。心(こころ)から人(ひと)の不幸(ふこう)を感(かん)じて、表(おもて)には出(だ)さないけれど胸(むね)を痛(いた)める人(ひと)もいました。とくに心(こころ)が弱(よわ)く、感(かん)じやすい役人(やくにん)がつらい罪人(ざいにん)や親(しん)せきを送(おく)るときには、思(おも)わず涙(なみだ)を流(なが)してしまうこともありました。
そのため、高瀬舟(たかせぶね)で罪人(ざいにん)を送(おく)る仕事(しごと)は、役人(やくにん)たちの間(あいだ)ではいやな仕事(しごと)でした。
二
いつごろの事(こと)だったでしょうか。たぶん江戸(えど)で松平(まつだいら)定信(さだのぶ)が政治(せいじ)をしていた寛政(かんせい)のころでしょう。智恩院(ちおんいん)というお寺(てら)の鐘(かね)が鳴(な)って、桜(さくら)が散(ち)る春(はる)の夕方(ゆうがた)でした。今(いま)までにない珍(めずら)しい罪人(ざいにん)が高瀬舟(たかせぶね)に乗(の)せられました。
その罪人(ざいにん)の名(な)は喜助(きすけ)で、三十歳(さんじゅっさい)くらいの、住(す)む所(ところ)が決(き)まっていない男(おとこ)でした。もともと親(しん)せきはいませんでした。ですから、牢屋敷(ろうやしき)に呼(よ)び出(だ)される人(ひと)もいないので、舟(ふね)には一人(ひとり)だけで乗(の)りました。
見張(みは)りのためにいっしょに舟(ふね)に乗(の)った役人(やくにん)は羽田(はねだ)庄兵衛(しょうべえ)でした。彼はただ「喜助(きすけ)は弟(おとうと)を殺(ころ)した罪人(ざいにん)だ」という事(こと)だけを聞(き)いていました。牢屋敷(ろうやしき)から高瀬舟(たかせぶね)まで連(つ)れて来(く)る間(あいだ)、庄兵衛(しょうべえ)はこの痩(や)せて青白(あおじろ)い顔(かお)の喜助(きすけ)の様子(ようす)を見(み)ていました。彼(かれ)はとても大人(おとな)しくて、真面目(まじめ)で、自分(じぶん)を役人(やくにん)としてしっかり尊敬(そんけい)して、素直(すなお)に従(したが)おうとしている事(こと)が分(わ)かりました。しかも、それは、罪人(ざいにん)によくあるような、大人(おとな)しいふりをして役人(やくにん)の気(き)に入(い)られようとする態度(たいど)ではありませんでした。
庄兵衛(しょうべえ)は不思議(ふしぎ)に思(おも)いました。そして舟(ふね)に乗(の)ってからも、ただ仕事(しごと)として見張(みは)るだけでなく、ずっと喜助(きすけ)の様子(ようす)に注意(ちゅうい)していました。
その日(ひ)は夕方(ゆうがた)から風(かぜ)がやみました。空(そら)いっぱいにかかった薄(うす)い雲(くも)が月(つき)をかすませていました。夏(なつ)の暖(あたた)かさが近(ちか)づいていて、川(かわ)の土(つち)から靄(もや)が出(で)るような夜(よる)でした。下京(しもぎょう)の町(まち)を離(はな)れ、加茂川(かもがわ)を渡(わた)るころには、あたりはしんとして、ただ舟(ふね)の先(さき)で水(みず)を切(き)る音(おと)だけが聞(き)こえていました。
夜(よる)の舟(ふね)の中(なか)では、罪人(ざいにん)も横(よこ)になって寝(ね)ることを許(ゆる)されていました。しかし喜助(きすけ)は横(よこ)になりませんでした。月(つき)の光(ひかり)が雲(くも)のせいで強(つよ)くなったり弱(よわ)くなったりするのを見(み)て、静(しず)かにしていました。その顔(かお)は明(あか)るく、目(め)はかすかに輝(かがや)いていました。
庄兵衛(しょうべえ)はさりげなく、ずっと喜助(きすけ)の顔(かお)を気(き)にしていました。そして心(こころ)の中(なか)で「不思議(ふしぎ)だ、不思議(ふしぎ)だ」と繰(く)り返(かえ)していました。なぜなら喜助(きすけ)の顔(かお)は、どこから見(み)ても楽(たの)しそうで、もし役人(やくにん)がいなければ、口笛(くちぶえ)を吹(ふ)いたり鼻歌(はなうた)を歌(うた)ったりしそうだったからです。
庄兵衛(しょうべえ)は思(おも)いました。これまで高瀬舟(たかせぶね)で何度(なんど)も罪人(ざいにん)を送(おく)ったが、みんなかわいそうで、辛(つら)い顔(かお)をしていた。それなのに、この男(おとこ)はどうしたのだろう。まるで遊(あそ)びで舟(ふね)に乗(の)っているような顔(かお)だ。罪(つみ)は弟(おとうと)を殺(ころ)したことだそうだ。だが、たとえ弟(おとうと)が悪人(あくにん)で、仕方(しかた)なく殺(ころ)したとしても、感情(かんじょう)を持(も)つ人間(にんげん)としては良(い)い気分(きぶん)ではないはずだ。この青白(あおじろ)いやせた男(おとこ)が、人(ひと)の心(こころ)をまったく持(も)たないほどの、すごい悪人(あくにん)なのだろうか。いや、そうは思(おも)えない。もしかして気(き)が狂(くる)っているのか。しかしそれなら、言葉(ことば)や行動(こうどう)がおかしいはずだが、少(すこ)しもそうではない。この男(おとこ)はどうしたのだろう…。庄兵衛(しょうべえ)は、考(かんが)えれば考(かんが)えるほど喜助(きすけ)の態度(たいど)が分(わ)からなくなりました。
三
しばらくして、庄兵衛(しょうべえ)は我慢(がまん)できなくなって、声(こえ)をかけました。
「喜助(きすけ)。お前(まえ)は何(なに)を考(かんが)えているんだ。」
「はい?」と言(い)って、喜助(きすけ)は辺(あた)りを見回(みまわ)しました。何(なに)か悪(わる)い事(こと)を役人(やくにん)に見(み)つけられたのではないかと心配(しんぱい)したのです。そして姿勢(しせい)を良(よ)くして庄兵衛(しょうべえ)の方(ほう)を見(み)ました。
庄兵衛(しょうべえ)は、仕事(しごと)と関係(かんけい)のない事(こと)を聞(き)く理由(りゆう)を説明(せつめい)しなければならないと思(おも)いました。それで、こう言(い)いました。「いや、特(とく)に理由(りゆう)があって聞(き)いたのではない。実(じつ)は、さっきからお前(まえ)が島(しま)へ行(い)く気持(きも)ちを聞(き)いてみたかったのだ。おれは今(いま)まで、この舟(ふね)で沢山(たくさん)の罪人(ざいにん)を島(しま)へ送(おく)ってきた。色々(いろいろ)な人(ひと)がいたが、みんな島(しま)へ行(い)くのを悲(かな)しんでいた。見送(みおく)りに来(き)た親戚(しんせき)といっしょに、一晩中(ひとばんじゅう)泣(な)くのが当(あ)たり前(まえ)だった。それなのに、お前(まえ)はどうも、島(しま)へ行(い)くのを辛(つら)く思(おも)っていないようだ。いったいお前(まえ)はどう思(おも)っているのだ。」
喜助(きすけ)はにっこり笑(わら)いました。「ご親切(しんせつ)におっしゃってくださって、ありがとうござます。確(たし)かに島(しま)へ行(い)くという事(こと)は、他(ほか)の人(ひと)にとっては悲(かな)しい事(こと)でしょう。その気持(きも)ちは、私(わたし)にも想像(そうぞう)することができます。しかしそれは、世(よ)の中(なか)で楽(らく)をしてきた人(ひと)だからです。京都(きょうと)はすばらしい町(まち)ですが、私(わたし)がここでしてきた苦(くる)しみは、他(ほか)のどこへ行(い)ってもないと思(おも)います。お上(かみ)※徳川幕府(とくがわばくふ)/のおかげで、命(いのち)が助(たす)かり、島(しま)へ送(おく)ってもらえるのです。島(しま)は辛(つら)い所(ところ)かもしれませんが、鬼(おに)がいるわけではありません。私(わたし)はこれまで、どこにも落(お)ち着(つ)いて住(す)むことができませんでした。今度(こんど)、お上(かみ)が島(しま)に住(す)めとおっしゃってくださいます。その住(す)めとおっしゃる場所(ばしょ)に落(お)ち着(つ)けることが、とても有(ありが)たい事(こと)です。それに私(わたし)は体(からだ)が弱(よわ)そうに見(み)えますが、病気(びょうき)になった事(こと)は一度(いちど)もありません。ですから島(しま)へ行(い)って、どんな辛(つら)い仕事(しごと)をしても、体(からだ)を壊(こわ)す事(こと)はないと思(おも)います。その上(うえ)、今回(こんかい)島(しま)へ送(おく)られる時(とき)に、二百文(にひゃくもん)のお金(かね)をいただきました。それをここに持(も)っています。」こう言(い)って、喜助(きすけ)は胸(むね)に手(て)を当(あ)てました。島(しま)へ送(おく)られる罪人(ざいにん)には、二百文(にひゃくもん)のお金(かね)を与(あた)えるという決(き)まりが当時(とうじ)ありました。
喜助(きすけ)は話(はな)し続(つづ)けました。「恥(は)ずかしい話(はなし)ですが、私(わたし)はこれまで二百文(にひゃくもん)というお金(かね)を自分(じぶん)で持(も)った事(こと)はありませんでした。仕事(しごと)をしたいと思(おも)って仕事(しごと)を探(さが)しました。仕事(しごと)が見(み)つかれば一生懸命(いっしょうけんめい)働(はたら)きました。でも、貰(もら)ったお金(かね)は、すぐに人(ひと)に渡(わた)さなければなりませんでした。現金(げんきん)で食(た)べ物(もの)を買(か)える時(とき)はまだ良(よ)い方(ほう)でした。たいていは借(か)りた物(もの)を返(かえ)して、また借(か)りる生活(せいかつ)でした。牢屋(ろうや)に入(はい)ってからは、仕事(しごと)をせずに食(た)べさせていただきました。それだけでも、お上(かみ)に申(もう)し訳(わけ)ない気持(きも)ちでした。それに牢屋(ろうや)を出(で)る時(とき)、この二百文(にひゃくもん)をいただきました。こうしてお上(かみ)の物(もの)を食(た)べながら、この二百文(にひゃくもん)を使(つか)わずに持(も)っていられるのです。自分(じぶん)のお金(かね)として手元(てもと)にあるというのは、私(わたし)にとっては初(はじ)めての事(こと)です。島(しま)へ行(い)ってどんな仕事(しごと)ができるかわかりませんが、この二百文(にひゃくもん)を使(つか)って仕事(しごと)を始(はじ)めようと思(おも)って、楽(たの)しみにしています。」こう言(い)って、喜助(きすけ)は口(くち)を閉(と)じました。
庄兵衛(しょうべえ)は「うん、そうか」と答(こた)えましたが、想像(そうぞう)もできなかった話(はなし)だったので、しばらく何(なに)も言(い)えなくて、黙(だま)っていました。
四
庄兵衛(しょうべえ)は、もう若(わか)くはありません。すでに妻(つま)と四人(よにん)の子(こ)どもがいて、さらに年寄(としよ)りの母(はは)もいるので、家(いえ)は七人家族(しちにんかぞく)です。普段(ふだん)の暮(く)らしはとても節約(せつやく)していて、人(ひと)から「けち」と言(い)われるほどです。着物(きもの)も仕事(しごと)で着(き)る物(もの)と、寝巻(ねま)きだけしか作(つく)りません。しかし不幸(ふこう)な事(こと)に、庄兵衛(しょうべえ)の妻(つま)はお金持(かねも)ちの商人(しょうにん)の家(いえ)から来(き)ました。妻(つま)は、夫(おっと)の給料(きゅうりょう)で暮(く)らそうとする気持(きも)ちはあります。でも、お金(かね)のある家(いえ)で大事(だいじ)に育(そだ)てられたので、夫(おっと)が満足(まんぞく)するほど厳(きび)しい節約(せつやく)をすることができません。月末(げつまつ)になると、お金(かね)が足(た)りなくなることがあります。その時(とき)、妻(つま)は実家(じっか)からこっそりお金(かね)を持(も)ってきて生活(せいかつ)に使(つか)います。これは、庄兵衛(しょうべえ)が借金(しゃっきん)をとても嫌(きら)っていたからです。けれども、そういう事(こと)は、やがて庄兵衛(しょうべえ)に知(し)られてしまいます。庄兵衛(しょうべえ)は、決(き)まったお祝(いわ)いの時(とき)に実家(じっか)から物(もの)や服(ふく)を貰(もら)うだけでも、良(よ)く思(おも)っていませんでした。ですから、生活費(せいかつひ)を貰(もら)ったと知(し)れば、機嫌(きげん)が悪(わる)くなりました。羽田(はねだ)の家(いえ)は普段(ふだん)は平和(へいわ)ですが、ときどき夫婦(ふうふ)が喧嘩(けんか)をするのは、この事(こと)が原因(げんいん)でした。
庄兵衛(しょうべえ)は今(いま)、喜助(きすけ)の話(はなし)を聞(き)いて、自分(じぶん)の生活(せいかつ)と比(くら)べてみました。喜助(きすけ)は、仕事(しごと)をしてもらったお金(かね)もすぐに取(と)られてしまうと言(い)いました。とてもかわいそうな暮(く)らしです。しかし、自分(じぶん)もお上(かみ)からもらう給料(きゅうりょう)をすぐに使(つか)い、結局(けっきょく)は残(のこ)らない暮(く)らしをしています。二人(ふたり)の違(ちが)いは、お金(かね)の「桁(けた)※単位(たんい)/の大(おお)きさ」が違(ちが)うだけです。そして、自分(じぶん)には喜助(きすけ)が喜(よろこ)んでいた二百文(にひゃくもん)の貯金(ちょきん)さえありません。
そう考(かんが)えてみると、喜助(きすけ)が二百文(にひゃくもん)を「貯金(ちょきん)」と思(おも)って喜(よろこ)ぶのも当然(とうぜん)です。その気持(きも)ちは理解(りかい)できます。しかし、不思議(ふしぎ)なのは、喜助(きすけ)が欲(よく)がなくて、少(すこ)しで満足(まんぞく)している事(こと)です。
喜助(きすけ)は仕事(しごと)を見(み)つけるのが大変(たいへん)でした。しかし仕事(しごと)が見(み)つかれば、一生懸命(いっしょうけんめい)働(はたら)いて、やっと食(た)べていけるだけで満足(まんぞく)していました。だから牢屋(ろうや)に入(はい)ってからは、働(はたら)かないで、食事(しょくじ)がもらえることに驚(おどろ)いて、生(う)まれて初(はじ)めての満足(まんぞく)を感(かん)じました。
庄兵衛(しょうべえ)はいくら考(かんが)えても、自分(じぶん)との間(あいだ)に大(おお)きな違(ちが)いがあると気(き)づきました。自分(じぶん)の暮(く)らしは、時々(ときどき)足(た)りない事(こと)はあっても、大体(だいたい)は何(なん)とかなって、生活(せいかつ)ができています。しかし、満足(まんぞく)を感(かん)じた事(こと)はほとんどありません。ふだんは幸(しあわ)せとも不幸(ふしあわ)せとも思(おも)わないで、生活(せいかつ)しています。でも、心(こころ)の奥(おく)では「もし仕事(しごと)をやめさせられたらどうしよう」「大(おお)きな病気(びょうき)になったらどうしよう」という不安(ふあん)があります。そして妻(つま)が実家(じっか)からお金(かね)を持(も)ってきて暮(く)らしを助(たす)けたと知(し)ると、その不安(ふあん)が強(つよ)くなっていきます。
この違(ちが)いはどこから来(く)るのでしょうか。表面(ひょうめん)だけを見(み)れば、「喜助(きすけ)には家族(かぞく)がいないが、自分(じぶん)にはいるからだ」と言(い)えます。しかし、それは本当(ほんとう)ではありません。たとえ自分(じぶん)が一人(ひとり)であっても、喜助(きすけ)のような心(こころ)にはなれないと思(おも)いました。本当(ほんとう)の事(こと)はもっと深(ふか)い所(ところ)にあるのだろうと庄兵衛(しょうべえ)は考(かんが)えました。
そして漠然(ばくぜん)と「人(ひと)の一生(いっしょう)とは何(なん)だろう」と思(おも)いました。人(ひと)は病気(びょうき)をすれば「病気(びょうき)でなければ良(よ)い」と思(おも)います。食(た)べ物(もの)がなければ「食(た)べていければ良(よ)い」と思(おも)います。貯金(ちょきん)がなければ「少(すこ)しでも貯金(ちょきん)があれば良(よ)い」と思(おも)います。貯金(ちょきん)があっても「もっとあれば良(よ)い」と思(おも)います。そうやって次(つぎ)から次(つぎ)へと望(のぞ)みが広(ひろ)がっていきます。人(ひと)はどこまで行(い)けば止(と)まることができるのでしょうか。その「止(と)まる」ことを今(いま)、目(め)の前(まえ)で見(み)せているのが喜助(きすけ)でした。
庄兵衛(しょうべえ)は驚(おどろ)きの目(め)で喜助(きすけ)を見(み)ました。その時(とき)、月(つき)を見上(みあ)げている喜助(きすけ)の頭(あたま)から、光(ひかり)が差(さ)しているように思(おも)えました。
五
庄兵衛(しょうべえ)は喜助(きすけ)の顔(かお)を見(み)ながら、また呼(よ)びかけました。「喜助(きすけ)さん」今度(こんど)は「さん」とつけましたが、深(ふか)い考(かんが)えがあって言(い)ったのではありませんでした。その声(こえ)が自分(じぶん)の口(くち)から出(で)て耳(みみ)に入(はい)った時(とき)、これはよくない呼(よ)び方(かた)だったと気(き)づきました。しかしもう言(い)ってしまった言葉(ことば)は取(と)り消(け)すことができません。
「はい」と答(こた)えた喜助(きすけ)も、「さん」と呼(よ)ばれたことを不思議(ふしぎ)に思(おも)ったらしく、おそるおそる庄兵衛(しょうべえ)の様子(ようす)を見(み)ました。
庄兵衛(しょうべえ)は気恥(きは)ずかしさを隠(かく)して言(い)いました。「いろいろと聞(き)いているが、お前(まえ)が島(しま)へ送(おく)られるのは、人(ひと)を殺(ころ)したからだと聞(き)いた。その理由(りゆう)をおれに話(はな)してくれないか。」
喜助(きすけ)はとても緊張(きんちょう)した様子(ようす)で、「かしこまりました」と言(い)って、小(ちい)さな声(こえ)で話(はな)し出(だ)しました。「わたくしは思(おも)いちがいをして、恐(おそ)ろしいことをしてしまいました。あとで思(おも)うと、どうしてあんなことができたのか自分(じぶん)でも不思議(ふしぎ)です。無我夢中(むがむちゅう)でしてしまいました。わたくしは子(こ)どものころ、両親(りょうしん)を病気(びょうき)で亡(な)くしました。そして弟(おとうと)と二人(ふたり)で残(のこ)されました。最初(さいしょ)は町(まち)の人(ひと)たちがかわいそうに思(おも)って助(たす)けてくださり、わたくしは近所(きんじょ)の人(ひと)の手伝(てつだ)いなどをして、なんとか生活(せいかつ)することができました。大(おお)きくなってからは、なるべく弟(おとうと)と離(はな)れず、いっしょに働(はたら)き、助(たす)け合(あ)いました。去年(きょねん)の秋(あき)には、西陣(にしじん)の織物(おりもの)の工場(こうば)で働(はたら)きました。そこで、わたくしは「空引(からひ)き」という仕事(しごと)をしました。しかしそのうち、弟(おとうと)が病気(びょうき)になり、働(はたら)けなくなりました。
わたくしたちは北山(きたやま)のほったて小屋(ごや)のような所(ところ)で暮(く)らしておりました。私(わたし)は紙屋川(かみやがわ)の橋(はし)を渡(わた)って工場(こうば)へ通(かよ)い、帰(かえ)りに食(た)べ物(もの)を買(か)って帰(かえ)りました。弟(おとうと)は『兄(あに)きにばかり苦労(くろう)をさせて申(もう)し訳(わけ)ない』とよく言(い)っておりました。ある日(ひ)、いつものように帰(かえ)ると、弟(おとうと)は布団(ふとん)に倒(たお)れていて、まわりは血(ち)だらけでした。私(わたし)はびっくりして、持(も)っていた物(もの)を放(ほう)り出(だ)し、そばへ行(い)って『どうしたんだ』と声(こえ)をかけました。弟(おとうと)は青(あお)い顔(かお)で、あごからほほにかけて血(ち)を流(なが)していて、声(こえ)が出(だ)せませんでした。息(いき)をするたびに、喉(のど)の傷(きず)からヒュウヒュウと音(おと)がするばかりでした。わたしにはどういうことかよく分(わ)かりませんでした。そこで「どうしたのだ、血(ち)を吐(は)いたのか」と言(い)って、弟(おとうと)のそばに近(ちか)づこうとしました。すると弟(おとうと)は右(みぎ)の手(て)を布団(ふとん)に突(つ)いて、少(すこ)し体(からだ)を起(お)こしました。左(ひだり)の手(て)はあごの下(した)を強(つよ)く押(お)さえていましたが、その指(ゆび)のあいだから黒(くろ)い血(ち)のかたまりが出(で)ていました。弟(おとうと)は、わたしがそばへ行(い)くのを止(と)めるように目(め)で合図(あいず)して、口(くち)をききました。やっと話(はな)せるようになったのです。『ごめん。どうか許(ゆる)してくれ。どうせ治(なお)らない病気(びょうき)だから、早(はや)く死(し)んで兄(あに)きを楽(らく)にしたいと思(おも)ったんだ。喉(のど)を切(き)ったらすぐ死(し)ねると思(おも)ったけど、息(いき)がもれるだけで死(し)ねない。力(ちから)いっぱい刃(やいば)を押(お)し込(こ)んだが、横(よこ)にすべってしまった。刃(やいば)は残(のこ)ってるようだ。これを抜(ぬ)いてくれれば死(し)ねると思(おも)う。苦(くる)しくてたまらない。どうか手(て)を貸(か)してくれ。抜(ぬ)いてくれ。』と弟(おとうと)は言(い)ったのです。弟(おとうと)が左(ひだり)の手(て)の力(ちから)を緩(ゆる)めると、またそこから息(いき)がもれます。わたしは、どう言(い)っていいか分(わ)からず、声(こえ)が出(で)ませんでした。黙(だま)って弟(おとうと)の喉(のど)の傷(きず)を見(み)てみると、弟(おとうと)は右手(みぎて)にかみそりを持(も)って横(よこ)に切(き)ったようなのです。ですが、それだけでは死(し)ねなかったようです。それで、そのかみそりをもっと深(ふか)く、突(つ)っ込(こ)んだように見(み)えました。かみそりの柄(え)は、やっと二寸(にすん)くらい傷口(きずぐち)から出(で)ていました。わたしはそれを見(み)て、どうしていいか分(わ)からず、弟(おとうと)の顔(かお)を見(み)ました。弟(おとうと)はじっとわたしを見(み)つめています。わたしはやっとのことで「待(ま)っていろ。医者(いしゃ)を呼(よ)んで来(く)る」と言(い)いました。弟(おとうと)は少(すこ)し恨(うら)めしそうな目(め)でわたしを見(み)ました。そして、また左手(ひだりて)で喉(のど)をしっかり押(お)さえて、「医者(いしゃ)を呼(よ)んでもだめだ。ああ、苦(くる)しい。早(はや)く抜(ぬ)いてくれ。お願い(ねがい)だ」と言(い)いました。わたしはどうしたらいいか分(わ)からなくて、ただ弟(おとうと)の顔(かお)だけを見(み)ていました。こんな時(とき)、不思議(ふしぎ)なことに、目(め)がいろいろなことを伝(つた)えます。弟(おとうと)の目(め)は「早(はや)くしろ、早(はや)くしろ」と言(い)って、恨(うら)めしそうにわたしを見(み)ています。わたしの頭(あたま)の中(なか)では、何(なに)かがぐるぐる回(まわ)っているような感(かん)じでした。弟(おとうと)の目(め)は恐(おそ)ろしい訴(うった)えを続(つづ)けます。それにその目(め)の恨(うら)めしさはだんだん厳(きび)しくなり、まるで敵(てき)をにらむような、怖(こわ)い目(め)になりました。それを見(み)て、わたしはとうとう、弟(おとうと)の言(い)うとおりにしなければならないと思(おも)いました。私(わたし)は『しかたがない、抜(ぬ)いてやる』と言(い)いました。すると弟(おとうと)の顔(かお)は明(あか)るくなり、とても嬉(うれ)しそうになりました。私(わたし)は、絶対(ぜったい)に一気(いっき)にやらなければならないと思(おも)いました。それで、膝(ひざ)を突(つ)いて体(からだ)を弟(おとうと)の方(ほう)へ乗(の)り出(だ)しました。弟(おとうと)は喉(のど)を押(お)さえていた左(ひだり)の手(て)の肘(ひじ)を布団(ふとん)に突(つ)いて、横(よこ)になりました。私(わたし)は剃刀(かみそり)の柄(え)をしっかり握(にぎ)って、ずずっと引(ひ)き抜(ぬ)きました。その時(とき)、入(い)り口(ぐち)の戸(と)を開(あ)けて、近所(きんじょ)のばあさんが入(はい)ってきました。留守(るす)の間(あいだ)、弟(おとうと)に薬(くすり)を飲(の)ませるなどの世話(せわ)をしてくれるおばあさんです。部屋(へや)の中(なか)はずいぶん暗(くら)くなっていましたから、おばあさんがどれだけ見(み)たかは分(わ)かりません。おばあさんは「あっ」と言(い)って、戸(と)を開(あ)けっ放(ぱな)しにして駆(か)け出(だ)していきました。剃刀(かみそり)を抜(ぬ)くとき、素早(すばや)く、まっすぐに抜(ぬ)こうとだけ気(き)をつけました。しかし、抜(ぬ)いたときの感(かん)じは、今(いま)まで切(き)れていなかった所(ところ)を切(き)ったように思(おも)えました。刃(やいば)が外(そと)の方(ほう)を向(む)いていましたので、外(そと)の方(ほう)が切(き)れたのでしょう。ばあさんがまた入(はい)ってきて、すぐにまた走(はし)って出(で)て行(い)きました私(わたし)はかみそりを握(にぎ)ったまま、それをぼんやり見(み)ていました。ばあさんが行(い)ってしまった後(あと)、弟(おとうと)を見(み)ると、弟(おとうと)はもう息(いき)をしていませんでした。傷口(きずぐち)からはたくさん血(ち)が出(で)ていました。その後(あと)、町(まち)の役人(やくにん)たちが来(き)て役場(やくば)へ連(つ)れて行(い)かれるまで、わたしはかみそりをそばに置(お)いて、目(め)を半分(はんぶん)あけたまま死(し)んでいる弟(おとうと)の顔(かお)をじっと見(み)ていました。
少(すこ)しうつむきながら、庄兵衛(しょうべえ)の顔(かお)を下(した)から見上(みあ)げて話(はな)していた喜助(きすけ)は、こう言(い)うと、目線(めせん)を膝(ひざ)に落(お)としました。
喜助(きすけ)の話(はなし)は、とても整理(せいり)されています。整理(せいり)されすぎているくらいです。これは、喜助(きすけ)が半年(はんとし)くらいの間(あいだ)事件(じけん)のことを何度(なんど)も思(おも)い出(だ)したことと、役場(やくば)で質問(しつもん)され、町奉行所(まちぶぎょうしょ)で調(しら)べられるたびに、注意深(ちゅういぶか)く思(おも)い出(だ)して話(はな)しをまとめていったからです。
庄兵衛(しょうべえ)は、まるでその場(ば)にいるように話(はなし)を聞(き)いていました。しかし、これは本当(ほんとう)に弟(おとうと)を殺(ころ)したことになるのだろうか、人(ひと)を殺(ころ)したことになるのだろうか、と話(はなし)を半分(はんぶん)聞(き)いた時(とき)から疑問(ぎもん)が起(お)こりました。話(はなし)を全部(ぜんぶ)聞(き)いても、その疑問(ぎもん)は消(き)えませんでした。弟(おとうと)は、かみそりを抜(ぬ)いてくれたら死(し)ねるだろうから、抜(ぬ)いてくれと言(い)いました。それを抜(ぬ)いて死(し)なせたのは、殺(ころ)したことになるでしょう。しかし、もしそのままにしていても、弟(おとうと)はどうせ死(し)ななければならなかったようです。弟(おとうと)が早(はや)く死(し)にたいと言(い)ったのは、苦(くる)しくてがまんできなかったからです。喜助(きすけ)は、その苦(くる)しみを見(み)ていることができませんでした。苦(くる)しみから助(たす)けるために、命(いのち)を終(お)わらせたのです。それは罪(つみ)でしょうか。殺(ころ)したことは、罪(つみ)です。しかし、それが苦(くる)しみから助(たす)けるためだったと考(かんが)えると、疑問(ぎもん)が起(お)こって、どうしても答(こた)えは出(で)ません。
庄兵衛(しょうべえ)はいろいろ考(かんが)えました。そして結局(けっきょく)、自分(じぶん)より上(うえ)の人(ひと)が決(き)めたことに従(したが)うしかないのだと思(おも)いました。それでも庄兵衛(しょうべえ)は、まだ納得(なっとく)できない気持(きも)ちが残(のこ)っていました。お奉行様(ぶぎょうさま)に聞(き)いてみたくてなりませんでした。
夜(よる)がだんだん深(ふか)くなっていきました。今(いま)は無言(むごん)の二人(ふたり)が乗(の)った高瀬舟(たかせぶね)は、黒(くろ)い水(みず)の上(うえ)をゆっくり進(すす)んでいきました。
当時遠島を申し渡された罪人は、もちろん重い科《とが》を犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために、人を殺し火を放ったというような、獰悪《どうあく》な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために、思わぬ科を犯した人であった。有りふれた例をあげてみれば、当時相対死《あいたいし》と言った情死をはかって、相手の女を殺して、自分だけ生き残った男というような類《たぐい》である。
そういう罪人を載せて、入相《いりあい》の鐘の鳴るころにこぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って、加茂川《かもがわ》を横ぎって下るのであった。この舟の中で、罪人とその親類の者とは夜どおし身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも返らぬ繰《く》り言《ごと》である。護送の役をする同心《どうしん》は、そばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷族《しんせきけんぞく》の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮《しょせん》町奉行の白州《しらす》で、表向きの口供《こうきょう》を聞いたり、役所の机の上で、口書《くちがき》を読んだりする役人の夢にもうかがうことのできぬ境遇である。
同心を勤める人にも、いろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って、耳をおおいたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役がらゆえ気色《けしき》には見せぬながら、無言のうちにひそかに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類とを、特に心弱い、涙もろい同心が宰領してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。
そこで高瀬舟の護送は、町奉行所の同心仲間で不快な職務としてきらわれていた。
――――――――――――――――
いつのころであったか。たぶん江戸で白河楽翁侯《しらかわらくおうこう》が政柄《せいへい》を執っていた寛政のころででもあっただろう。智恩院《ちおんいん》の桜が入相《いりあい》の鐘に散る春の夕べに、これまで類のない、珍しい罪人が高瀬舟に載せられた。
それは名を喜助《きすけ》と言って、三十歳ばかりになる、住所不定《じゅうしょふじょう》の男である。もとより牢屋敷《ろうやしき》に呼び出されるような親類はないので、舟にもただ一人《ひとり》で乗った。
護送を命ぜられて、いっしょに舟に乗り込んだ同心羽田庄兵衛《はねだしょうべえ》は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて牢屋敷から棧橋《さんばし》まで連れて来る間、この痩肉《やせじし》の、色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙《しんびょう》に、いかにもおとなしく、自分をば公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが、罪人の間に往々見受けるような、温順を装って権勢に媚《こ》びる態度ではない。
庄兵衛は不思議に思った。そして舟に乗ってからも、単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に、細かい注意をしていた。
その日は暮れ方から風がやんで、空一面をおおった薄い雲が、月の輪郭をかすませ、ようよう近寄って来る夏の温《あたた》かさが、両岸の土からも、川床《かわどこ》の土からも、もやになって立ちのぼるかと思われる夜《よ》であった。下京《しもきょう》の町を離れて、加茂川を横ぎったころからは、あたりがひっそりとして、ただ舳《へさき》にさかれる水のささやきを聞くのみである。
夜舟《よふね》で寝ることは、罪人にも許されているのに、喜助は横になろうともせず、雲の濃淡に従って、光の増したり減じたりする月を仰いで、黙っている。その額は晴れやかで目にはかすかなかがやきがある。
庄兵衛はまともには見ていぬが、始終喜助の顔から目を離さずにいる。そして不思議だ、不思議だと、心の内で繰り返している。それは喜助の顔が縦から見ても、横から見ても、いかにも楽しそうで、もし役人に対する気がねがなかったなら、口笛を吹きはじめるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。
庄兵衛は心の内に思った。これまでこの高瀬舟の宰領をしたことは幾たびだか知れない。しかし載せてゆく罪人は、いつもほとんど同じように、目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船《ゆさんぶね》にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪いやつで、それをどんなゆきがかりになって殺したにせよ、人の情《じょう》としていい心持ちはせぬはずである。この色の青いやせ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの、世にもまれな悪人であろうか。どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや。それにしては何一つつじつまの合わぬことばや挙動がない。この男はどうしたのだろう。庄兵衛がためには喜助の態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。
――――――――――――――――
しばらくして、庄兵衛はこらえ切れなくなって呼びかけた。「喜助。お前何を思っているのか。」
「はい」と言ってあたりを見回した喜助は、何事をかお役人に見とがめられたのではないかと気づかうらしく、居ずまいを直して庄兵衛の気色《けしき》を伺った。
庄兵衛は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言いわけをしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。「いや。別にわけがあって聞いたのではない。実はな、おれはさっきからお前の島へゆく心持ちが聞いてみたかったのだ。おれはこれまでこの舟でおおぜいの人を島へ送った。それはずいぶんいろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へゆくのを悲しがって、見送りに来て、いっしょに舟に乗る親類のものと、夜どおし泣くにきまっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へゆくのを苦にしてはいないようだ。いったいお前はどう思っているのだい。」
喜助はにっこり笑った。「御親切におっしゃってくだすって、ありがとうございます。なるほど島へゆくということは、ほかの人には悲しい事でございましょう。その心持ちはわたくしにも思いやってみることができます。しかしそれは世間でらくをしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまでわたくしのいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上《かみ》のお慈悲で、命を助けて島へやってくださいます。島はよしやつらい所でも、鬼のすむ所ではございますまい。わたくしはこれまで、どこといって自分のいていい所というものがございませんでした。こん度お上《かみ》で島にいろとおっしゃってくださいます。そのいろとおっしゃる所に落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたい事でございます。それにわたくしはこんなにかよわいからだではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってから、どんなつらい仕事をしたって、からだを痛めるようなことはあるまいと存じます。それからこん度島へおやりくださるにつきまして、二百文《もん》の鳥目《ちょうもく》をいただきました。それをここに持っております。」こう言いかけて、喜助は胸に手を当てた。遠島を仰せつけられるものには、鳥目二百銅をつかわすというのは、当時の掟《おきて》であった。
喜助はことばをついだ。「お恥ずかしい事を申し上げなくてはなりませぬが、わたくしは今日《こんにち》まで二百文というお足《あし》を、こうしてふところに入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取りつきたいと思って、仕事を尋ねて歩きまして、それが見つかり次第、骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭《ぜに》は、いつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられる時は、わたくしの工面《くめん》のいい時で、たいていは借りたものを返して、またあとを借りたのでございます。それがお牢《ろう》にはいってからは、仕事をせずに食べさせていただきます。わたくしはそればかりでも、お上《かみ》に対して済まない事をいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出る時に、この二百文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上《かみ》の物を食べていて見ますれば、この二百文《もん》はわたくしが使わずに持っていることができます。お足を自分の物にして持っているということは、わたくしにとっては、これが始めでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが、わたくしはこの二百文を島でする仕事の本手《もとで》にしようと楽しんでおります。」こう言って、喜助は口をつぐんだ。
庄兵衛は「うん、そうかい」とは言ったが、聞く事ごとにあまり意表に出たので、これもしばらく何も言うことができずに、考え込んで黙っていた。
庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を四人生ませている。それに老母が生きているので、家は七人暮らしである。平生人には吝嗇《りんしょく》と言われるほどの、倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻しかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸な事には、妻をいい身代《しんだい》の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう扶持米《ふちまい》で暮らしを立ててゆこうとする善意はあるが、ゆたかな家にかわいがられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしてゆくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内証で里から金を持って来て帳尻《ちょうじり》を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のようにきらうからである。そういう事は所詮《しょせん》夫に知れずにはいない。庄兵衛は五節句だと言っては、里方《さとかた》から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては、里方から子供に衣類をもらうのでさえ、心苦しく思っているのだから、暮らしの穴をうめてもらったのに気がついては、いい顔はしない。格別平和を破るような事のない羽田の家に、おりおり波風の起こるのは、これが原因である。
庄兵衛は今喜助の話を聞いて、喜助の身の上をわが身の上に引き比べてみた。喜助は仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな、気の毒な境界《きょうがい》である。しかし一転してわが身の上を顧みれば、彼と我れとの間に、はたしてどれほどの差があるか。自分も上《かみ》からもらう扶持米《ふちまい》を、右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我れとの相違は、いわば十露盤《そろばん》の桁《けた》が違っているだけで、喜助のありがたがる二百文《もん》に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。
さて桁を違えて考えてみれば、鳥目《ちょうもく》二百文をでも、喜助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは喜助の欲のないこと、足ることを知っていることである。
喜助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口を糊《のり》することのできるだけで満足した。そこで牢《ろう》に入ってからは、今まで得がたかった食が、ほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。
庄兵衛はいかに桁《けた》を違えて考えてみても、ここに彼と我れとの間に、大いなる懸隔《けんかく》のあることを知った。自分の扶持米《ふちまい》で立ててゆく暮らしは、おりおり足らぬことがあるにしても、たいてい出納《すいとう》が合っている。手いっぱいの生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感ぜずに過ごしている。しかし心の奥には、こうして暮らしていて、ふいとお役が御免になったらどうしよう、大病にでもなったらどうしようという疑懼《ぎく》が潜んでいて、おりおり妻が里方から金を取り出して来て穴うめをしたことなどがわかると、この疑懼が意識の閾《しきい》の上に頭をもたげて来るのである。
いったいこの懸隔はどうして生じて来るだろう。ただ上《うわ》べだけを見て、それは喜助には身に係累がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれはうそである。よしや自分が一人者《ひとりもの》であったとしても、どうも喜助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、庄兵衛は思った。
庄兵衛はただ漠然《ばくぜん》と、人の一生というような事を思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食ってゆかれたらと思う。万一の時に備えるたくわえがないと、少しでもたくわえがあったらと思う。たくわえがあっても、またそのたくわえがもっと多かったらと思う。かくのごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏み止まることができるものやらわからない。それを今目の前で踏み止まって見せてくれるのがこの喜助だと、庄兵衛は気がついた。
庄兵衛は今さらのように驚異の目をみはって喜助を見た。この時庄兵衛は空を仰いでいる喜助の頭から毫光《ごうこう》がさすように思った。
――――――――――――――――
庄兵衛は喜助の顔をまもりつつまた、「喜助さん」と呼びかけた。今度は「さん」と言ったが、これは充分の意識をもって称呼を改めたわけではない。その声がわが口から出てわが耳に入《い》るや否や、庄兵衛はこの称呼の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出たことばを取り返すこともできなかった。
「はい」と答えた喜助も、「さん」と呼ばれたのを不審に思うらしく、おそるおそる庄兵衛の気色《けしき》をうかがった。
庄兵衛は少し間《ま》の悪いのをこらえて言った。「いろいろの事を聞くようだが、お前が今度島へやられるのは、人をあやめたからだという事だ。おれについでにそのわけを話して聞せてくれぬか。」
喜助はひどく恐れ入った様子で、「かしこまりました」と言って、小声で話し出した。「どうも飛んだ心得違いで、恐ろしい事をいたしまして、なんとも申し上げようがございませぬ。あとで思ってみますと、どうしてあんな事ができたかと、自分ながら不思議でなりませぬ。全く夢中でいたしましたのでございます。わたくしは小さい時に二親《ふたおや》が時疫《じえき》でなくなりまして、弟と二人《ふたり》あとに残りました。初めはちょうど軒下に生まれた犬の子にふびんを掛けるように町内の人たちがお恵みくださいますので、近所じゅうの走り使いなどをいたして、飢え凍えもせずに、育ちました。次第に大きくなりまして職を捜しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたして、いっしょにいて、助け合って働きました。去年の秋の事でございます。わたくしは弟といっしょに、西陣《にしじん》の織場《おりば》にはいりまして、空引《そらび》きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。そのころわたくしどもは北山《きたやま》の掘立小屋《ほったてごや》同様の所に寝起きをいたして、紙屋川《かみやがわ》の橋を渡って織場へ通《かよ》っておりましたが、わたくしが暮れてから、食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、わたくしを一人《ひとり》でかせがせてはすまないすまないと申しておりました。ある日いつものように何心なく帰って見ますと、弟はふとんの上に突っ伏していまして、周囲《まわり》は血だらけなのでございます。わたくしはびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かを、そこへおっぽり出して、そばへ行って『どうしたどうした』と申しました。すると弟はまっ青《さお》な顔の、両方の頬《ほお》からあごへかけて血に染まったのをあげて、わたくしを見ましたが、物を言うことができませぬ。息をいたすたびに、傷口でひゅうひゅうという音がいたすだけでございます。わたくしにはどうも様子がわかりませんので、『どうしたのだい、血を吐いたのかい』と言って、そばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床《とこ》に突いて、少しからだを起こしました。左の手はしっかりあごの下の所を押えていますが、その指の間から黒血の固まりがはみ出しています。弟は目でわたくしのそばへ寄るのを留めるようにして口をききました。ようよう物が言えるようになったのでございます。『すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせなおりそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄きにらくがさせたいと思ったのだ。笛《ふえ》を切ったら、すぐ死ねるだろうと思ったが息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って、力いっぱい押し込むと、横へすべってしまった。刃はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたらおれは死ねるだろうと思っている。物を言うのがせつなくっていけない。どうぞ手を借して抜いてくれ』と言うのでございます。弟が左の手をゆるめるとそこからまた息が漏ります。わたくしはなんと言おうにも、声が出ませんので、黙って弟の喉《のど》の傷をのぞいて見ますと、なんでも右の手に剃刀《かみそり》を持って、横に笛を切ったが、それでは死に切れなかったので、そのまま剃刀を、えぐるように深く突っ込んだものと見えます。柄《え》がやっと二寸ばかり傷口から出ています。わたくしはそれだけの事を見て、どうしようという思案もつかずに、弟の顔を見ました。弟はじっとわたくしを見詰めています。わたくしはやっとの事で、『待っていてくれ、お医者を呼んで来るから』と申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉《のど》をしっかり押えて、『医者がなんになる、あゝ苦しい、早く抜いてくれ、頼む』と言うのでございます。わたくしは途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は、不思議なもので、目が物を言います。弟の目は『早くしろ、早くしろ』と言って、さも恨めしそうにわたくしを見ています。わたくしの頭の中では、なんだかこう車の輪のような物がぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなって来て、とうとう敵《かたき》の顔をでもにらむような、憎々しい目になってしまいます。それを見ていて、わたくしはとうとう、これは弟の言ったとおりにしてやらなくてはならないと思いました。わたくしは『しかたがない、抜いてやるぞ』と申しました。すると弟の目の色がからりと変わって、晴れやかに、さもうれしそうになりました。わたくしはなんでもひと思いにしなくてはと思ってひざを撞《つ》くようにしてからだを前へ乗り出しました。弟は突いていた右の手を放して、今まで喉を押えていた手のひじを床《とこ》に突いて、横になりました。わたくしは剃刀《かみそり》の柄をしっかり握って、ずっと引きました。この時わたくしの内から締めておいた表口の戸をあけて、近所のばあさんがはいって来ました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、わたくしの頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ内のなかが暗くなっていましたから、わたくしにはばあさんがどれだけの事を見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり、表口をあけ放しにしておいて駆け出してしまいました。わたくしは剃刀《かみそり》を抜く時、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いた時の手ごたえは、今まで切れていなかった所を切ったように思われました。刃が外のほうへ向いていましたから、外のほうが切れたのでございましょう。わたくしは剃刀を握ったまま、ばあさんのはいって来てまた駆け出して行ったのを、ぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから、気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からはたいそうな血が出ておりました。それから年寄衆《としよりしゅう》がおいでになって、役場へ連れてゆかれますまで、わたくしは剃刀をそばに置いて、目を半分あいたまま死んでいる弟の顔を見詰めていたのでございます。」
少しうつ向きかげんになって庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助は、こう言ってしまって視線をひざの上に落とした。
喜助の話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ち過ぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時の事を幾たびも思い浮かべてみたのと、役場で問われ、町奉行所《まちぶぎょうしょ》で調べられるそのたびごとに、注意に注意を加えてさらってみさせられたのとのためである。
庄兵衛はその場の様子を目《ま》のあたり見るような思いをして聞いていたが、これがはたして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いた時から起こって来て、聞いてしまっても、その疑いを解くことができなかった。弟は剃刀《かみそり》を抜いてくれたら死なれるだろうから、抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいても、どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦《く》を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解けぬのである。
庄兵衛の心の中には、いろいろに考えてみた末に、自分よりも上のものの判断に任すほかないという念、オオトリテエに従うほかないという念が生じた。庄兵衛はお奉行《ぶぎょう》様の判断を、そのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、庄兵衛はまだどこやらにふに落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。
次第にふけてゆくおぼろ夜に、沈黙の人二人《ふたり》を載せた高瀬舟は、黒い水の面《おもて》をすべって行った。
